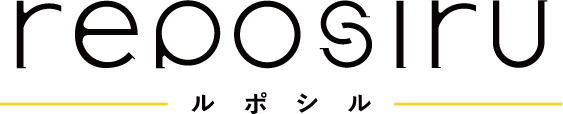“ありがとう、お互いさま”と
互いを思いやり、数十年
未来に残る職場環境の育まれ方
【所沢ロイヤル病院】
※この仕事は募集終了いたしました。ご応募ありがとうございました。
“チームの力”は、多くの病院や企業が、自らの長所として挙げやすい項目です。
しかし、そのクオリティは千差万別。風土や文化と呼べる域にまで達しているところは、まだまだ少ないのかもしれません。
所沢ロイヤル病院では、働く人それぞれが“ありがとう、お互いさま”と手を差し伸べ合い続け、最適な労働環境を育み続けてきたそうです。
“ワークライフバランス”や“働き方改革”など
それぞれに最適な就労環境が模索され始めて、しばらくの時が経ちました。
一般的には、大企業やベンチャー企業、IT系の企業などが先鋭的な取り組みの成功例として取り上げられています。
しかし、そのようなトレンドが訪れる以前から職員のことを心から大切にする文化を育み、すでにワークライフバランスの構築が完了している病院が存在します。
西武池袋線の小手指駅から西に約2kmほど。
住宅や畑が広がる空が広い環境の中に建てられている所沢ロイヤル病院も、そのひとつ。

治療を目的とする急性期の医療を行う病院に対し療養をメイン業務とする慢性期患者のための病院で、
医療、リハビリテーション、介護などの多職種連携により在宅に戻ることを目的に、さまざまなサービスを提供しています。
小手指駅南口から、国道463号バイパス経由でバスに揺られること約8分。
「所沢ロイヤル病院前」バス停に到着しました。
周囲を見渡すと、この一帯には病院やクリニック、介護施設などが建ち並び、ひとつの街区を形成しています。
所沢ロイヤル病院は、この“所沢ロイヤル・ワム・タウン”というグループ内の医療やリハビリ、療養施設を集めたエリアの中で慢性期の医療を行う基幹病院という位置付けです。

ガラス張りの開放的な雰囲気のエントランスをくぐると、受付が見えてきました。
 午後遅めの時間だったので、診察を受ける人の姿はすでになくとても静かな雰囲気です。
午後遅めの時間だったので、診察を受ける人の姿はすでになくとても静かな雰囲気です。
職員さんに案内され、3階の取材を行う場所に向かう途中でどこからともなく、談笑の声が聞こえてきました。
今日、お話を伺う3名の方々が、すでに待っていてくれたのです。
 自然な笑顔。
自然な笑顔。
それが、所沢ロイヤル病院の方々とお会いしたときの最初の印象です。
職場環境が根本的に良くなければ、“自然な笑顔”は決して生まれません。
所沢ロイヤル病院が育んできたであろう和気あいあいとした雰囲気が、お会いして数秒で、すでに伝わってきます。
どうして、院内に笑顔があふれているのでしょう。看護部長の砂川さんに、話を伺いました。
「“ありがとう、お互いさま”と、お互いをフォローし合うことが、もう何十年も続いています。」
「業務の細かいことはもちろん、勤務時間や勤務日の融通といったことも、お互いさまの精神で、乗り越えています。」
特に、育児をしている人は子どもが突発的な病気にかかったり行事などで手いっぱいになることが多く、仕事と育児の両立は、永遠のテーマ。
しかし、その課題は、すでに25年以上前に砂川さんが若手だった頃には、解消されていたそうです。
「出産・育児と仕事を両立できず、勤めていた大学病院を退職しました。」
「それから数年後、子どもも大きくなってきたので、そろそろ大好きな看護の現場に戻りたいと考えたときに、近所のこの病院の存在に気が付きました。」
週に数日だけの非常勤で復職を希望した砂川さん。
募集要項を見てみると保育室完備、非常勤で週数日からOKなどまさに理想とする条件が書かれていました。
しかし、入職してから、想像は良い方に裏切られます。
「驚いたのは、勤め始めてしばらくした頃、子どもが熱を出してしまった時のことです。」
「仕事に穴を空けてはいけないとなんとか出勤した私に、当時の看護師長さんは、『何をやっているの!お母さんは一人しかいないのよ!今日はもう帰ってお子さんの面倒を見てあげなさい』と話されました。」
「もう、ありがたくて、ありがたくて。」

この日は、看護師長さんの言うとおり、帰宅して子どものケアに専念したそうです。
そして、お子さんの回復を待って、数日後、病院に帰ってきました。
その時に、看護部長さんが話してくれたのは、
“ありがとう、お互いさま”
という文化が所沢ロイヤル病院にはあるということ。
穴をあけたことは事実だけれども他の人が同じ状況になったときに、
“お互いさま”と気持ち良くフォローすれば、それでOKというものでした。
「聞けば、看護師長さんや看護部長さんも、若手の子育て世代の時に同様の経験をされたとのことです。」
「この手厚いサポートを生む “職員同士がフォローし合う精神”に感動し、いまもここに居ついているんです(笑)」
“ありがとう、お互いさま”の精神は
ごくごく日常的な風景だそうです。
たとえば、夕方に救急車がやってきたとします。

もちろん、保育園へ預けている子どものお迎えがあるお母さんは定時までで帰らなくてはなりません。
つまり、残っているスタッフだけで、救急車への対応を行うのですが、
“どうすればベストの対応を目指せるか”はもちろん“既存の業務との役割分担”などについてもすぐに全員で考え始め、数分後にはそれぞれが動き始めるとのことです。
そして、定時で帰ったスタッフは後日、何の指示もなくても“あの時はありがとうね。いま、私、これやっておくね”と埋め合わせをしているそうです。
これは、全院内、全病棟に共通すること。
まさしく、所沢ロイヤル病院の“文化”といえるでしょう。
砂川さんが話されたことをまさにいま体験しているのが、看護師の藤倉さんです。
「現在、小学校低学年の長男と、2歳の次男がいます。長男を妊娠した時も仕事を続けていたのですが、つわりがとてもひどく、退職せざるをえませんでした。」
「でも、看護の仕事が好きなんだと思います。長男が育って手がかからなくなり始めてすぐに、復職を考えました。」
当時は府中に住んでいたという藤倉さん。
ご家庭の都合もあり、出産後すぐに小手指に引っ越してきたそうです。

「看護師になりたての頃は、難病の患者さんが入院されている病棟で、とにかくスキルの向上を目指しました。」
「多くの人もそうだと思いますが、一定のレベルで仕事ができるようになると、次は興味を持ったジャンルに進みたくなります。」
「そこで、府中の病院に転職し、回復期リハビリの看護を学び始めました。しかし、これからという時に妊娠し、退職になってしまいました。」
「あの続きをしたいと切望していた時に目にしたのが、近所の所沢ロイヤル病院の求人というわけです。」
仕事が好きなら、誰しも自らのキャリアアップを目指します。
しかし、出産を望む女性の場合はキャリアが分断されてしまうことは、ご存知のとおり。
子どもをちゃんと育てたい。でも、看護の仕事にも戻りたい。
藤倉さんにとって、その願いを叶えてくれたのが、所沢ロイヤル病院でした。
「子どもの送り迎えや急な発熱などがどうしてもあるので、まずは非常勤から始めたいと考えていました。」
「所沢や小手指エリアは待機児童が多いと聞いていたので、“保育室あり”の文字を見て、ここだ!と思いました。」
それからしばらくして、藤倉さんは非常勤として回復期リハビリの看護の仕事を再開できたそうです。
それでは続いて、現在の藤倉さんの仕事を拝見しましょう。
所沢ロイヤル病院で勤続6年、看護師経験10年以上の藤倉さんは病棟内に3つあるうちのひとつのチームリーダーを任されています。
 案内されてやって来たのは、“回復期リハビリテーション病棟”。
案内されてやって来たのは、“回復期リハビリテーション病棟”。
治療が一段落し、リハビリなど在宅に戻る準備をする患者さんがたくさんおられます。
「通常の病棟と違うところがすごく多いですね。」
「回復期の方々なので、元気で賑やか。リハビリテーション職やMSW(医療ソーシャルワーカー)など、医師以外の多職種と連携することが多く、とても勉強になります。」

当然、患者さんそれぞれで、家庭環境や家族構成、収入などが異なるため、
退院の支援の仕方もカスタマイズしてその人に最適な支援をしていくことが求められます。
「介護のことをより知らなければならないと考えるようになりました。」
「MSWの方々にもたくさん教えてもらい、ケアマネージャーの資格も取得しようと勉強を始めています。より、その人に最適な在宅復帰の支援をしたいので。」
特に次男を身ごもってからの産休と育休の期間は時間を見つけては、ケアマネージャー関連の参考書をたくさん読み込んだとのこと。
ただ、勉強をすればするほど、得た知識を現場で活用したい、専門職の人と意見交換をしたいなど仕事への欲求が高まってしまったそうです。

「リーダーになっても、勉強することばかりです。」
「患者様によりよい看護を提供したいし、そのためには、スキルアップは必須。医療も時が経つごとに進化し、現場で行う作業も変わってきます」
座学も、ケーススタディも、看護師にとっては大切な学びの機会。
しかし、藤倉さんには、もっと大切な勉強の場があるそうです。
「何よりも患者様との会話が最も勉強になります。」
「当院は、高齢者の方が多いため、人生の大先輩がほとんど。日常的な会話の中にも参考になることがたくさんあります。」
「また、何でもないような雑談の中からでも、医療や看護のヒントはたくさん見つかります。看護師にとって最も大切なのはコミュニケーション能力かもしれませんね」
今日も、所沢ロイヤル病院のナースステーションや病室ではたくさんの会話が生まれ、藤倉さんたちはより良い看護を目指して、奮闘していることでしょう。
仕事を通じて自己実現をしている方として紹介いただいたのが、
病棟で介護福祉士として働く、水上さんです。
なんと前職は、成田空港でグランドスタッフだったとのこと。
どうして。小手指にやってきたのでしょう?
なぜ、介護職に就いたのでしょう?
「実家がこの近所なのですが、20年ほど前に父が倒れて介護が必要になったことが、すべてのきっかけです。介護職の仕事を身近に見て、興味を持ちました。」

実は、グランドスタッフに戻ろうと思えば戻れた水上さん。
しかし、新しい道を選択することにしました。
それは、どうしてでしょう?
「内容としてやってみたい気持ちが強かったことが最大の理由ですが、歳を重ねても長く続けられる仕事で、場所も選ばないことも大きかったです」
「やろうと決めてから、すぐにスクーリングに行って、介護職員初任者研修(当時はヘルパー2級)の資格を取得しました。」
「とはいえ、未経験でしたから、本当に雇用してもらえるかは、いつも心配でしたが、無事、入職することができました。」
早速、介護職としての仕事を始めた水上さん。先輩がひとつずつ細かいことでも丁寧に教えてくれたことで順調に素質を開花させていきました。

しかし、新人時代には悩みもあったそうです。
「ある程度の覚悟はしていましたが、患者様ごとにご要望が大きく異なるのです。」
「意図を汲み取って、良かれと思ってやってみても、ほとんどが間違い。解決の糸口を求めていましたね。」
「改善できたのは、先輩たちの動きを見て、相談も受けてもらう中で、まだまだ自分本位だったことに気づかされたためです」
特に代表的な例は、入浴だったそうです。
「どうしても、1日のスケジュールの中に入っていることから“こなさなければならないミッション”と、とらえていました」

患者様の状況や要望に合わせてケアを変更することもできます。
例えば、入浴の代わりに温かいタオルで体を拭くなど、スケジュールをうまく入れ替えて、気分転換してもらうこともできる。
いま振り返ってみると、解決するための方法はたくさんあります。
しかし、“しなければならない”と考えていた若い水上さんには思い付かなかったことでした。
先輩の存在が、水上さんを救ったといえます。

そんな水上さんには、思い出に残る患者さんがいるそうです。
「末期がんの患者様で、痛みを緩和するお薬を飲んだ後でも気分がすぐれないようでした。」
「介護職としてできることは何かと考えたときに、ふと思い出したのが、父の介護のこと。」
「実際に、父にしていたのと同様に、手を握り、お話を聞き、背中をずっとさすり続けたところ、安心されたのか、無事、お休みになられました。」
次の日、その患者さんが自ら、話しかけてきました。
“昨日はありがとう、あれは助かりました”
“また、つらい時はお願いします。”
過去に体験したことが、スキルとして活きる瞬間に誰しもが仕事に携わる喜びに気づきます。
未経験でこの業界に飛び込んできてから、すでに15年。
水上さんもまた、チームリーダーとして抜擢されていました。
そこで、所沢ロイヤル病院で介護職として活躍するために必要なことは何か質問してみました。
「当然、医療と接する分野なので、ある程度はケガや病気の知識が必要になります。」
「さらに、トランスや食事介助などは、技術も必要。でも、私をご覧ください。未経験で入職しましたが、先輩たちにたくさんのことを教えてもらい、勉強も積み重ねたことで、リーダーになれました。」
「振り返って思うのは、興味とやる気が最重要ということ。技術や知識は入職してからでも間に合います」
最後に、再び、砂川さんを訪ね、所沢ロイヤル病院に向いている人について聞いてみました。
 「ゆっくりでも、丁寧な人が当院に向いていると思います。」
「ゆっくりでも、丁寧な人が当院に向いていると思います。」
「急性期ではできなかった看護に、じっくりと取り組んでみたい方。いったん離職しても、再び看護師をやりたいという方。子育て中の方。」
「人員要件の観点からは、十分スタッフは足りていますが、“ありがとう、お互いさま”の文化を、ゆとりを持って育み続けるには、もう少し、スタッフを増やさなければなりません。」
「もちろん、新しく来ていただく方にも“ありがとう、お互いさま”の輪の中に入っていただきます。」
「ワークライフバランスへの配慮と福利厚生にはどこにも負けないものがあると信じていますので、ぜひ、興味がある方に来てほしいです。」
良い仕事をするために、最も必要なもの。それは、心身ともに健康であること。
楽しく学びある看護の現場づくりは長い年月をかけて整備され、未来へ受け継がれようとしています。